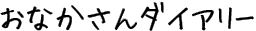先生にお任せが当たり前と思っていた
いま入院しているこの病院、T病院はこれまで、外来で10年以上ずっと診てもらってきた私の「かかりつけ」の病院です。ただし、かかりつけといっても潰瘍性大腸炎に限ってのことです。規模の大きな大学病院なので、風邪をこじらせたりしたときにまで診てもらうには勝手が悪く、そういう日常的に体調を悪くしたときには、自宅近所のクリニックで診てもらっています。
私がT病院で潰瘍性大腸炎を診てもらうようになった経緯は、単にたまたまというだけのことです。それまで住んでいた九州から東京に引っ越すことになり、それに伴って前の主治医が紹介してくださったのが、T病院でした。そのときはほとんど先生にお任せで、自分で積極的にこの病院を選んだわけではありませんでした。今、もし同じ状況になれば、もっと熱心に自分自身で調べたうえで病院を決めて、こちらから先生にお願いして紹介状を書いてもらったでしょうが、その頃は医師や病院のことを主体的に調べるという意識がまだ低かったのです。というより、専門家である先生の指示にそのまま従うことが当たり前だと思っていました。
裏切られた不満解消目的の転院の試み
その頃は寛解状態が続いていたということもあって、新しくT病院に変わってからも、とくに不満はありませんでした。しかし、新たな主治医は、患者の主体性に任せる傾向が強いタイプで、それがこちらからすると、あまり親身になってくれないと映ることもありました。とくにその時の私は、医者に対して「指示待ち」姿勢でしたから、なおさらそのように感じられたわけです。なので、病状が再燃した時に、そのような主治医の姿勢に不満を募らせ、別の病院を受診したことがありました。そこは私立の大学病院でUC治療に関してはよく知られていたので、期待をもって受診したところ、いきなり来られても迷惑だと言わんばかりの、冷たく追い返されるような対応をされたのです。たしかに、紹介状も、それまでの診療データも何一つ持って来ずに、いままでの病院は嫌だからなんとかしてくれ、と突然やって来られたら、そういう対応になってしまうのも無理はありません。今となってはそう理解できますが、そのことがあってからは、もう嫌になって転院のことは考えなくなりました。
ほかの病院のことは分かりませんが、T病院では担当主治医が頻繁に替わりました。最初に担当した先生こそ、5、6年間担当してくださっていたのですが、その先生がT病院を退職されて以降は、ほぼ毎年のように担当医が交代しました。大学病院の先生というのは、診てもらっている患者からすれば、教授であろうが助教であろうが、等しく自分を診てくれる臨床医ですが、その仕事の中身というか、カバーしている範囲には随分と違いがあります。これはもちろん経験やスキルといった能力の差によるものがあるでしょうが、それと同じかそれ以上に、教授、助教という立場の差によるものが大きいのではないかと思います。患者の目線から見ていると、大学病院の先生は講師、助教と立場が下位になるほど、現場レベルの細々としたことに追われていたり、頻繁に担当部局が変わったり、別の研究所や大学に移ったりしていて、忙殺されているようです。最初の5、6年間私の主治医だった先生は、教授でありまたT病院の副院長でもあるというような「偉い」立場の先生でしたが、その後に担当した主治医は皆、助教でした。担当医が頻繁に入れ替わった背景にはこのようなことがあるのだと思います。
このように頻繁に主治医は入れ替わるし、また先に述べたように別の大学で冷たい対応をされたという経験もあって、私は医者に対して淡々と接するようになりました。しかし淡々とというのは、自分自身で主体的に調べたり、考えたりしたうえで、医者に冷静に接していた、ということではなくて、病気や医者や病院についてあれこれ考えることを単に面倒臭がって放棄していただけのはなしです。それで、今回、手術の可能性ありと診断されたときにも、どこか他人事にような気がしていたのです。しかし、具体的な術式などに話が及ぶにつれて、さすがにこれはちゃんと調べたほうがいいと思い、ネットを漁りはじめました。