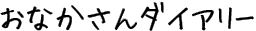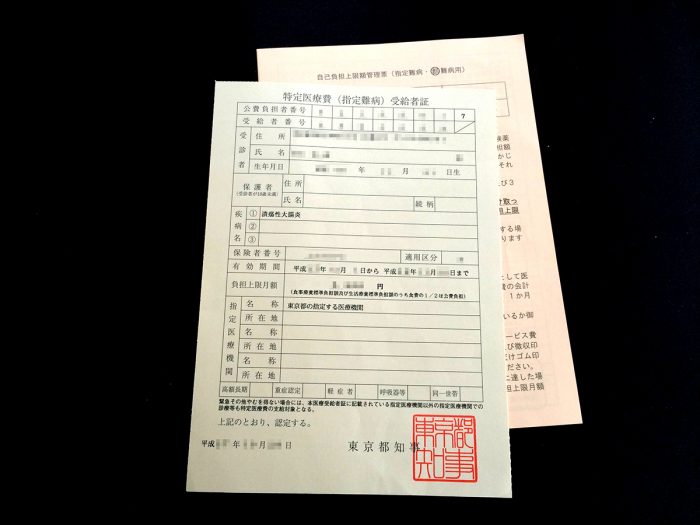
特定医療費(指定難病)受給者証
難病医療費助成制度とは
入院することになったら、やはり気になるのはお金のことです。潰瘍性大腸炎は指定難病なので、患者は治療費に対する公的助成を受けることができます。私は、発病してから長年この助成制度にはお世話になってきましたが、今回入院することになってあらためてこの制度のありがたみが身にしみました。そこで、この難病医療費助成制度について少し触れてみたいと思います。ひとつ断っておかなければならないのですが、ここで述べることは、基本的に私が住んでいる東京都についての事例です。この制度は国が定めている制度ですが、各種手続きや審査、認定などの実際の運営は都道府県が行っています。基本的な仕組みは変わりませんが、各自治体によって具体的な細かな部分が違うことも考えられますのでその点はご了承ください。なお、この難病医療費助成制度は、2015年から制度内容が新しくなっています。56だった対象疾患の数も306まで大幅に拡大され、負担上限の金額やその条件も見直されました。それまで負担額が無料だった重症患者にも所得に応じて負担を求めるなど、全体的に「広く薄く」支援する制度に変わっています。難病医療費助成制度についてのより詳しい情報は厚生労働省または各自治体のホームページなどをご覧ください。
自分のかかった病気が指定難病である人は、自治体(都道府県)に所定の申請手続きを行い、審査に通れば、特定医療費受給者として認められます。受給者として認められれば、患者が負担するのは毎月の負担上限額までで、それ以上は、入院費、外来診察費の区別なく、いくらかかっても治療費はすべて助成によって賄われます(入院時の食費は別です)。この自己負担上限の金額は、おもに患者本人の所得に応じて定められており、0円~30,000円まで6段階に分けられています。また、特定医療費受給者の場合、認定を受けたその疾患に関しての診療費は、一様に2割負担となっており、自己負担上限額よりもその金額のほうが低い場合は、患者の負担は2割のみでよいことになっています。
非常に大きな経済的支え
では、特定医療費受給者は具体的にいくらくらいの助成金を受けることができるのでしょうか。例として今回の私の入院をみてみましょう。退院後、支払いが済んだあとに確認したのですが、かかった金額はだいたい次のようなものでした。10日間の入院期間で、検査を6種類ほど受けて、診療費(診察、診断、検査など)と食費、また保険適用外である特別室使用料(差額ベッド代)等ももろもろ含めた総額はおよそ45万円。このうち患者負担として私が支払った金額は27,000円程度でした。ただしこの金額のほとんどは特別室使用料が占めており、仮に差額が発生しない通常の病室を利用していたとすれば5,000円ほどで済む計算です。仮にこれが、医療費助成がなかったとしたら、通常の健康保険の適用で3割負担ですから、13万円を超える額を支払わなければならなかったことになります。助成のあるなしの差がいかに大きいかがこれだけを見てもよくわかります。
わかりづらい制度内容、煩雑な手続き
このように、難病医療費助成制度は難病患者にとって、経済面での非常に大きな支えになります。しかも病状が重く頻繁に入退院を繰り返したり、若い時に発症した(=病気を抱える期間が長い)人ほどその恩恵は大きなものになります。しかしこれだけ支援が手厚いということは裏を返せば、ここに費やされている公費も膨大だということです。したがって、受給者の認定には最大限の公平性や正確性が求められるため(というよりもお役所仕事だからということもあると思いますが)、定められている条件や規定が細かいので、利用者にとっては大変分かりづらく、申請手続きも非常に煩雑なものになっています。とくに2015年から制度内容が刷新されたことも、さらにそれを助長しています。私自身も新制度になって中身がどう変わったのかをちゃんと理解するようになったのはごく最近のことで、それまでは制度内容を説明している書類やネットの情報を見ても、お役所文書特有のわかりにくさ全開なので、読む気がしなかったのです。
たとえば、自己負担上限額とは無関係に、すべての特定医療費受給者は、認定を受けたその疾患に関しての診療費は、一様に2割負担となっていますが、これは旧制度では3割で、国民健康保険と同じ割合でした。ですから、以前私は、負担上限額が高く設定されていた時分に、しばらく更新せず認定をはずしていたことがありました。その頃は1、2ヶ月に1回程度外来診察を受診するだけでしたので、診療費や薬代が上限金額を超えることはまずなく、認定を受けている利点が全くなかったのです。(実は後になって「全くない」ことはないと分かりました。これについては後述します。)利点がないのであればわざわざ、申請書類に添付する診断書作成のためにつらい内視鏡検査を受けたり、煩雑な申請手続きをやったりする意味はないので、更新申請をしていませんでした。私はその後再燃したのでふたたび申請して認定再開しましたが、もしかしたら、新制度になって3割から2割に変わったことを知らないまま、これと同じような理由で認定をあえてはずしたままにしている人が相当数いるのではないかと思います。それくらい、周知が行き渡っていないのです。そこで、次回の記事では、ポイントになると思われる項目を絞って列挙してみることにします。