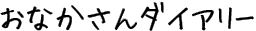制度のポイント
難病医療費助成制度の中身を詳しく知ろうとして厚労省のホームページなどを見ると、詳細までしっかりと解説されているのですが、なにが利用者にとっての要点なのかが判然とせず、また説明の表現が分かりにくいところもあったりするので、いくつかポイントを絞って列挙してみました。
- 受給者の所得に応じて一ヶ月ごとの自己負担上限額がそれぞれに定められており、その額は0円~30,000円の間で6段階になっている。
- 自己負担上限額は一ヶ月ごとの外来診察、入院費および薬代、また複数の医療機関や薬局などを利用した場合はそれらを合計して算定する。
- 上記自己負担上限額とは別に、特定医療費受給者の自己負担割合は2割と定められており、自己負担上限額よりも2割の金額のほうが低い場合、自己負担額はその低い方の金額、つまり2割となる。
- 受給対象となるのは認定されている指定難病に関する診療費のみであって、それ以外の疾患は対象外。例えば私が風邪で診てもらっても、その診療費や薬代は助成の対象にはならない。
- 特定医療費受給者が助成を受けられるのは、都道府県の指定する指定医療機関(病院、薬局等)を受診してかかった診療費のみ。
- 受給者認定の有効期間は1年間。認定継続を希望する場合は毎年更新手続きを行い審査を受けなければならない。
- 受給認定の申請には、都道府県の指定する指定医が作成した臨床調査個人票(診断書)を添付する必要がある。
助成制度の存在が患者に知らされない場合もある
上のリスト中のとくに5.や7.などは、実は私自身このような規定があることをつい最近まで知りませんでした。私の場合は、普段利用している病院や薬局がたまたま指定医療機関で、主治医がたまたま指定医だったからよかったのですが、人によっては、これを知らなかったばかりに病院や主治医を変えなければならず、煩わしい思いをしなければらないということもありえます。
このように制度内容のわかりづらさもさることながら、それどころか難病患者がこの制度の存在そのものを知らないケースも少なからずあるようです。私について言えば、発病した時に最初に診断した先生が、このような制度があることをちゃんと教えてくださったので、すぐに手続きすることができました。しかし中には制度の存在を知らない医者もいますし、知っていても、単純に伝え忘れることもあるし、もう知ってるだろうと医者が思い込んでいて患者に伝えないこともあります。
私は医療費助成申請については、幸い、不都合がありませんでしたが、別の事で似たようなことがありました。それは携帯電話料金についてのことです。携帯電話会社は障害者や指定難病受給者に対する料金の割引サービスをやっています。各社でその内容には差はありますが、主要3キャリアはどこも同様のサービスを提供しています。2008年頃にはすでに提供されていたという情報があるので、もう10年近く前からやっていたようですが、私がこの存在を知ったのは今年(2016年)のはじめになってからでした。知るやいなや、手続きをするためにすぐにショップに駆け込みました。私がショップの店員に、もっと早く知っていれば・・・とこぼすと、「こればかりは、こちらから積極的に確認したりお勧めしたりということができないものですから・・・」との答え。もっともな話です。
情報はこちらから取りに行かなくてはいけない
医療費助成制度にしろ、携帯電話料金の割引にしろ、この種のことは、積極的に告知がされていないために、こちらから情報を取りに行かない限りは利益を受けられないことがほとんどです。そのうえ手続きが煩雑だったりすれば、どうしても利用が遠のいてしまうのも無理はありません。また、とくに発病したての時は、こういった支援をいちばん必要とする時期なのですが、それにもかかわらず、症状のことや、病気にかかったという事実を受け止めることで頭が一杯で、なかなかそこまで考えが及ばないものです。それでもやはりこういった支援は、先に述べたように、金銭的には間違いなく患者の大きな支えになりますし、それがひいてはストレスを緩和して病気そのもののケアにもつながります。ですから、難病患者の方、とくに、不幸にもつい最近そう診断されてしまったという方には、こういった支援制度やサービスが提供されているということをまず知っていただき、億劫さをなんとか抑えてでも情報に触れて、すすんで利用してほしいと思います。
情報の入手先としては何と言ってもインターネットがまずは手っ取り早いのですが、それだけではどうしても個人が発信する二次的、三次的情報(このブログもその一つですが)に偏りがちになるし、古かったり誤りがあったりということもあります。そのため、それ以外の情報源も欲しいところですが、その入口として、大変参考になる本がありますのでここで紹介しておきます。
『難病患者の教科書【2016年5月版】』 浅川透著 日本ブレインウェアFunction5出版部
難病になった不安に対する心の持ち方、考え方についてのアドバイスから、ここでお話した特定医療費助成制度についての具体的な解説、生命保険や医療保険には入れないのかとか、難病患者の就労はどこまで可能か、あるいは病気についてを相談を受け付けたり情報を提供してくれる機関の紹介など、難病患者が知りたいと思っているが、どこに聞けばよいかわからないという情報を実用的な形でまとめてあります。医師によって書かれた病気そのものや治療についての本、あるいは患者が書いた闘病記などは多く出ていますが、この本のように難病患者の社会生活についてアドバイスしたものは、ほかにはほとんどないと思います。難病患者になったばかりの人はもちろん、これまで長く病気を抱えている人にとっても非常に有益だと思いますので、ぜひ読んでみてください。